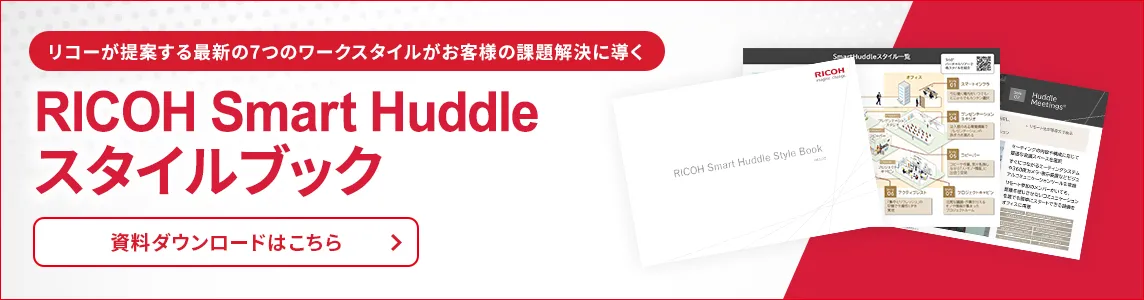データから見る多様化する働き方~求められる背景や取り組み例を解説~
近年企業は、リモートワークやフレックスタイム制、副業解禁など、様々な働き方を取り入れることで、従業員の満足度向上や生産性の向上を目指しています。本コラムでは、データを基に多様化する働き方の現状と、その背景にある社会的要因、さらに取り組み例と、メリットや課題、解決策、実際の導入事例について解説します。働き方の多様化が企業へいかに貢献するのか見ていきましょう。
データから見る多様な働き方
雇用型就業者のテレワーカー(雇用型テレワーカー)(※1)の割合は、全国で24.8%(1.3ポイント減)となった。全国的に減少傾向である一方で、コロナ禍以前よりは高い水準を維持している。特に首都圏では、R4年度調査よりも1.9ポイント減少となったものの約4割の水準を維持している。
コロナ禍以降の直近1年間のテレワーク実施率は、全国どの地域においても減少傾向であったが、コロナ流行前よりは高水準であると推測される。
テレワーク実施頻度については、直近1年間のうちにテレワークを実施した雇用型テレワーカーにおいては、週1~4日テレワークを実施する割合が増えており、コロナ禍を経て出社とテレワークを組み合わせるハイブリッドワークが拡大傾向にあると言える。
出典:国土交通省ウェブサイト

人々のライフスタイルは時代と共に変化しており、その時代に適したニーズに合うような働き方を、企業が従業員へ提供することが求められています。
なぜ多様な働き方が求められるのか
続いて多様な働き方が求められる背景を見ていきましょう。
働く人のニーズの変化
かつては、仕事がプライベートよりも重要視される傾向がありましたが、近年では、女性の社会進出やダイバーシティの推進が進み、働き手が趣味や家事・育児などのプライベートも仕事と同様に重視する考え方にシフトしつつあります。特に若い世代を中心に、仕事を通じて自己実現を図りつつも、ワークライフバランスを重視する価値観が広まっています。このため、働き手は個人のスタイルやライフステージに合った柔軟な働き方を求めるようになっているのです。

人事戦略の変化
自然災害やパンデミックといった緊急事態に備えた事業継続計画(Business Continuity Planning)の一環として、リモートワークを人事戦略に取り入れる企業が増えています。これは、従業員の安全確保と事業の中断を最小限に抑えるための重要な取り組みです。加えて、オフィス以外の場所でも業務が可能になることで、万が一の事態でも迅速に事業を継続できる体制が構築できます。これにより、従業員は安全かつ柔軟に働けるようになり、企業はリスクを軽減できます。
高齢化や人口減少による労働力不足
少子高齢化が進む日本では、生産年齢人口の減少が深刻な課題となっています。このため、企業は優秀な人材を確保することが難しくなり、従来の働き方だけでは労働力の維持が困難になりつつあります。この課題を解決するため、育児や介護と両立したい人、地方在住者、定年後のシニア世代など、さまざまな事情を持つ人々が働きやすくなるよう、多様な働き方を導入する企業が増えています。こうした取り組みは、労働力の確保と同時に、企業競争力の維持・向上にもつながります。
多様な働き方に対しての取り組み例
リモートワーク
リモートワークとは、情報通信技術(ICT)を利用して、自宅やコワーキングスペースなど、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことです。
ワーケーション
ワーケーションとは、ワーク(仕事)とバケーション(休暇)を組み合わせた言葉で、リモートワーク等を活用し、観光地やリゾート地など通常のオフィスから離れた場所で自分の時間を過ごしつつ、働くスタイルのことです。

フレックスタイム制
フレックスタイム制とは、労働者が日々の出勤・退勤時間や労働時間を自分で決定することで、生活と仕事のバランスを取りながら効率よく働ける仕組みです。
時差出勤や時短勤務
時差出勤とは、決められた時間の範囲の中で、出退勤時間を選べる働き方のことで、時短勤務とは、育児や介護などの事情がある従業員が所定労働時間よりも短い時間で勤務できる制度のことです。
副業・兼業
副業は、本業以外の仕事で収入を得ることで、兼業は、本業と同等の他の仕事を掛け持ちすることです。
多様な働き方のメリットと課題
続いて多様な働き方を導入することで得られるメリットと課題について見ていきます。
多様な働き方のメリット
多様な働き方は、働き手にとって魅力的な条件のひとつです。ワークライフバランスが注目されている近年、リモートワークとオフィス勤務の柔軟性を提供することで、優秀な人材を確保することができます。
柔軟な勤務形態やリモートワークの導入により、従業員は仕事と私生活のバランスを取りやすくなり、ストレスが軽減されます。これにより、従業員の満足度が向上し、離職率が低下します。

自宅での作業が苦手な人もいれば、オフィスでは集中できないと感じる人もいます。企業が多様な働き方を従業員へ提供することで、個々の生産性を高めることができます。
導入コストなど、短期で見るとコストはかかりますが、優秀な人材の確保や従業員の生産性の向上、また専用のデスクを割り振らないフリーアドレスにすることで、オフィスにかかるコストの削減が見込めます。
多様な働き方の課題
現在のオフィス環境ではリモートワークに対応するのが難しい場合、専用のツールの導入や新しいオフィス家具の購入が求められます。また、従業員が自由に働く場所を選択できるようにするためには、個人用のタブレットやパソコンの支給が必要です。
多様な働き方ができるようになる一方で、働くスタイルが具体的にイメージしにくい従業員が増え、新しい働き方へ適応するための時間がかかる可能性があります。自主性が求められるため、特に経験の浅い従業員や新人には十分なサポートが不可欠です。
オフィス以外の場所で働く場合、情報の漏洩リスクも増加します。自宅やカフェなど、オフィス外での作業環境では、セキュリティ対策が十分でない場合が多く、機密情報の漏洩や不正アクセスのリスクが高まります。企業は、セキュリティ対策を強化し、適切なITサービスやツールの整備を進める必要があります。
多様な働き方で直面する課題の解決策
先ほど、課題として取り上げた、導入コスト、一定期間を要する、技術的な課題についての解決策をご紹介します。
従業員の声を取り入れる
導入コストがかかるという課題については、一度に導入するのではなく、優先順位の高い順に導入することが解決策の一つです。優先順位を決めるには現状把握が欠かせませんが、その際に現場の従業員の生の声を取り入れることで、問題の深刻度が手に取るようにわかるでしょう。

定着までのサポートの仕組みを作る
特にリモートワークなどの在宅勤務を含む働き方を導入する場合に、自主性が求められるため、定着に時間を要します。この場合は、自主性をサポートするための仕組み作りがポイントになります。
例えばこれまではオフィスの会議室でチームで話し合ってプロジェクトの企画や提案、計画を策定していた場合、リモートワークにおいては各自がそれぞれ提案事項を提出するといったフローにすることが挙げられます。他人任せにできず自ら提案しなければ前に進まない状況をあえて作ることで、自主性を引き出すことが可能です。
その他、社内SNSやビジネスチャットで自ら業務内容の報告やレポーティングの機会を設けるのもおすすめです。
ITツールの導入・運用の支援を受ける
ITツールの選定や導入・運用などの技術的な課題は、自社ですべてまかなおうとせず、専門家の支援を受けるのも一案です。第三者の視点で客観的に自社の課題を見つめることができ、専門的知見を有するため、より良い解決策とツールの提案を受けられます。
単なるツールの導入ベンダーではなく、導入時もビジネス課題に即した選定と成果につながる運用までの支援を受けられる専門会社を選ぶようにしましょう。
【企業タイプ・規模別】多様な働き方の導入事例
すでに多くの企業では多様な働き方を導入し、有効な成果につなげています。企業タイプ・規模別に導入事例をご紹介します。
大企業 社会ニーズに対応する必要性のあるライフスタイルに関わる不動産事業
ある大手不動産会社は、多様化する顧客ニーズを背景とし、ライフスタイルを支援する事業者として、社内で多様な働き方を推進することで、自社の価値を最大化する必要がありました。
そこで多様な働き方の観点では、主に次の取り組みを推進しています。

トップメッセージなどによる意識改革
全従業員対象リモートワーク制やコアタイムなしのスーパーフレックス整備などのインフラ整備
事業所内保育所の設置やフレックス型の育児時短勤務制度、出産・育児に関する面談制度、産育休復帰時研修など
リモートワーク制度の導入や介護費用補助制度などの環境整備
65歳の定年後の雇用と活躍の場の提供
大企業 IT企業としてスマートに楽しく働ける環境作りを目指す
あるIT企業は、ITとAIを活用して従業員がスマートかつ楽しく働ける環境づくりを目指す働き方改革推進の一環として、スーパーフレックスタイム制を導入しています。
これは従来のフレックスタイム制のコアタイムを撤廃し、従業員が業務内容や状況に応じて始業・就業時刻を日々変更できる制度です。
従業員一人一人がより効率の良い時間帯で働けるようになることで成果の最大化を目指しています。
中小企業 病気でも働き続けられる環境整備で人材定着率向上につなげる
ある水産業の中小企業は従業員の病気(がん)の告知を機会に治療しながら働き続けられる環境整備を進めました。
他の従業員も親の介護などとの両立ができるよう、13パターンの勤務時間帯を設定し、人材定着率を高めています。
また人材不足の課題もあったため、外国人や障がい者雇用にも力を入れました。
これらの施策の結果、雇用の安定化が実現したほか、人材定着により1.5倍の生産性向上効果につながりました。
中小企業 派遣社員を採用する企業で短時間正社員制度などの工夫で業績向上
ある包装関連の中小企業では、派遣社員も採用していたが、優秀でありながら時間が限られるなどの理由で、社内で十分な実力の発揮ができていないことを知りました。
そこで、派遣社員の正社員登用や短時間正社員制度導入などの柔軟な働き方の拡充を図りました。
その結果、従業員は働き方のニーズが満たされつつ、実力を発揮できるようになり、会社としては業績アップにつながりました。
多様な働き方によって起きている変化
前述の事例を受けて、多様な働き方を推進した結果、どのような変化が起きたのか確認していきましょう。
成果の最大化による生産性向上
リモートワークやフレックスタイム制、育児や介護、治療との両立をサポートする制度導入などを受け、従業員一人ひとりが業務効率化と生産性向上を実現できます。
その結果、組織活動としての成果が最大化し、生産性向上につながっています。

ワークライフバランスの実現
働く場所と時間をある程度選べる制度は、子育てや育児とのワークライフバランスを実現します。
例えばスーパーフレックス制を活用し、子どもと触れ合う時間や送り迎えの時間が創出できた従業員もいます。
スキルアップの促進
多様な働き方の推進は、従業員自らのスキルアップも支援します。これまで時間に縛られてできなかった独学を進められたり、外国人研修の導入により社内のスキルが底上げされる効果が期待できます。
まとめ
本コラムでは、多様な働き方について、必要性や取り組み例、メリットや課題、解決策、導入事例まで幅広く解説しました。近年注目されている「多様な働き方」は、これからより良い人材の確保、職場環境を目指す企業にとって一つの解決策になりうるでしょう。
無料資料ダウンロード
RICOH Smart Huddle スタイルブック
この一冊で、最新の7つのワークスタイルが分かり、お客様の課題を解決に導きます。
こんな方にオススメ!
- 生産性が向上するオフィスにリニューアルしたいが、イメージが湧かない
- 働く場所にとらわれず、コミュニケーションを円滑化したい
- お客様の記憶に残るエントランスを演出したい など
掲載内容
- RICOH Smart Huddleスタイル一覧
- リコーが提案する7つのスタイル
- 課題解決に導くラインナップ
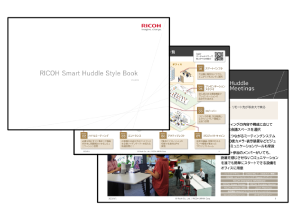
お問い合わせ
サービスや価格に関する質問などお気軽にご相談ください。